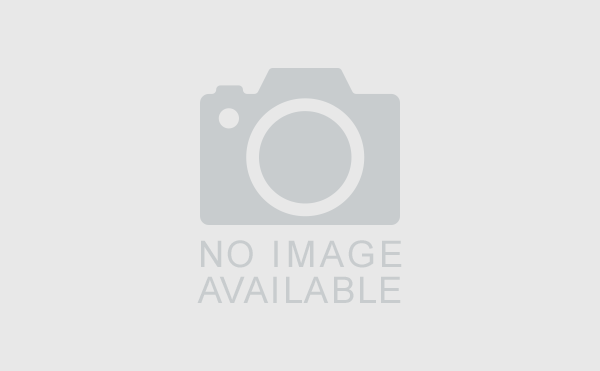日本における養蚕業の歴史とは!?
1、古代〜奈良時代(伝来と普及の始まり)
・養蚕は中国から伝わったとされ、日本では 弥生時代末期〜古墳時代 にはすでに行われていたと考えられています。
・『日本書紀』や『古事記』にも、養蚕や絹に関する記述があります。
・奈良時代には、絹は貴族や朝廷にとって非常に貴重な繊維で、朝貢品や税として納められていました。
2、平安〜鎌倉時代(絹の文化的価値)
・平安時代、絹は宮廷文化に欠かせない高級織物の素材として用いられました。
・鎌倉時代には武士階級が台頭しましたが、彼らの衣装にも絹が使われ、養蚕は徐々に農村に広がっていきます。
3、 江戸時代(養蚕の普及と発展)
・江戸時代には、養蚕は農民の副業として全国に普及。
・特に信州(長野県)、上州(群馬県)、甲州(山梨県)などが大きな産地として発展しました。
・「蚕影信仰」や「お蚕さま」を祀る風習が広まり、養蚕は生活と深く結びついた産業になります。
4、 明治時代(近代化と世界的輸出産業へ)
・明治維新後、西洋への絹輸出が日本の外貨獲得の大きな柱となりました。
・「富岡製糸場」(1872年設立)は近代的製糸工場の代表例で、日本の産業近代化の象徴。
・日本の生糸は「ジャパン・シルク」として世界的に高評価を受け、輸出の最重要品目となりました。
5、 大正〜昭和(産業の転換期)
・大正期には養蚕農家が最盛期を迎え、日本は世界一の生糸輸出国となります。
・しかし昭和に入ると化学繊維(レーヨン、ナイロンなど)の登場や世界恐慌、戦争の影響で需要が減少。
・戦後も衣料用途の絹需要は減少し、養蚕業は縮小の道をたどります。
6、 現代(養蚕の新しい展開)
・現在、日本の養蚕は大規模産業ではなくなりましたが、伝統工芸用の絹糸や高級着物用の絹として存続。
・同時に、蚕を利用した 医療・食品・バイオ研究 が進展しています。
・蚕粉末を活用した健康食品(例:イミノシュガー含有)
・シルク由来の化粧品や医療用素材(人工皮膚・縫合糸など)
・遺伝子組換え蚕による医薬品タンパク質の生産
◆ まとめ
日本の養蚕は・・・
・古代には貴族文化を支える存在
・江戸期には農村経済を支える副業
・明治期には輸出で国を支える基幹産業
・現代には伝統産業+先端バイオ研究の素材
として、その時代ごとに役割を変えながら続いてきました。