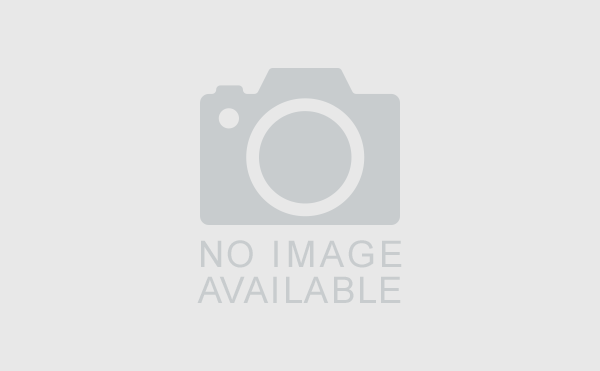なぜ「糖尿病・高血圧」が認知症リスクと関係すると考えられるのか
1、血管障害・脳血流低下
高血圧や動脈硬化、微小血管障害は脳への血流供給を阻害し、虚血性変化や慢性的な酸素・栄養不足をもたらすと考えられます。これが神経細胞死や神経ネットワークの破綻を誘発する可能性があります。
2、血管性認知症との重なり
高血圧・糖尿病は脳血管障害(脳梗塞、微小出血、白質変化など)を起こしやすく、これらは典型的な血管性認知症の原因となります。さらに、認知症患者のなかには「混合型(アルツハイマー病と血管性の混在)」が多く、血管負荷が発症や進行を加速するという見方があります。
3、インスリン抵抗性/糖代謝異常
糖尿病およびインスリン抵抗性があると、脳内のグルコース代謝異常、酸化ストレス、炎症応答亢進、アミロイドβやタウ蛋白の異常代謝などが進む可能性が指摘されています。いわゆる「脳のインスリン抵抗性」仮説が近年注目されています。
4、腎機能・微小血管との共通性
先述のアルブミン尿の報告は、腎(腎小体・糸球体)や小血管系の障害が脳の微小血管系と類似の脆弱性を持つという観点から、「腎−脳連関」の可能性を示しています。
5、炎症・酸化ストレス・代謝異常
糖尿病・高血圧によって慢性的な低度炎症、酸化ストレス、内皮機能障害が進み、これが血管・神経系に悪影響を与えることで認知機能低下を促すという仮説もあります。
◆降圧治療・血圧管理は、単に心血管リスク抑制だけでなく、認知機能維持や認知症予防の文脈でも有望な介入対象になる可能性が強まりつつある。
→ 特に、従来の標準目標より厳格な降圧(intensive control)が有効であるという証拠が増えてきている(例:SPRINT MIND のフォローアップ解析)
→ コミュニティベースの血圧介入で認知症リスクを低下させ得るという実証研究も報じられている(中国農村地域)
◆大規模コホートやバイオバンクを活用し、血液バイオマーカーやゲノム情報を活かして、「どの人に」「どの程度の介入が効くか」を理解しようとする研究が始まっている(例:ユタ大学での研究)
University of Utah Healthcare
◆腎機能指標(アルブミン尿など)が認知症リスクと関連する可能性という報告は、認知症リスク評価の新たな指標として興味深く、血管・腎・脳の連関を改めて意識させます。
◆なお、非常高齢(90歳以上)集団では、従来リスク因子との関連が見えにくくなる、あるいは逆転する可能性も指摘されており、高齢期におけるリスク因子の扱いには注意が必要という示唆もあります。